広報誌「ひろば」の案内

複雑な構造のエネルギーのお話や誤解の多い放射線に関する情報を、広く一般の方々にわかりやすくお伝えするため隔月(奇数月)に発行しております。
せとふみの e report
- 525号(2024年7月)
エネルギーミックスを支える現場から―技術者たちの思い―~東北電力株式会社 新潟火力発電所~
要約版|全文(PDF) - 524号(2024年5月)
エネルギーミックスを支える現場から―技術者たちの思い―~量子科学技術研究開発機構(QST)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所~
要約版|全文(PDF) - 523号(2024年3月)
エネルギーミックスを支える現場から―技術者たちの思い―~東北電力株式会社 原町火力発電所~
要約版|全文(PDF) - 522号(2024年1月)
エネルギーミックスを支える現場から―技術者たちの思い―~日本原燃株式会社 再処理事業所 再処理工場~
要約版|全文(PDF) - 521号(2023年11月)
エネルギーミックスを支える現場から―技術者たちの思い―~電源開発株式会社 鬼首地熱発電所~
要約版|全文(PDF) - 520号(2023年9月)
エネルギーミックスを支える現場から―技術者たちの思い―~東北電力株式会社 女川原子力発電所~
要約版|全文(PDF) - 519号(2023年7月)
エネルギーミックスを支える現場から―技術者たちの思い―~東京電力リニューアブルパワー株式会社神流川発電所~
要約版|全文(PDF) - 518号(2023年5月)
エネルギーミックスを支える現場から―技術者たちの思い―~東北電力東新潟火力発電所~
要約版|全文(PDF) - 517号(2023年3月)
「脱炭素を目指す取り組み」高温ガス炉~国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗研究所高温ガス炉研究開発センター~
要約版|全文(PDF) - 516号(2023年1月)
「再エネ拡大に向けた取り組み」洋上風力発電~秋田洋上風力発電株式会社(展示施設:AOW 風みらい館)~
要約版|全文(PDF) - 515号(2022年11月)
「脱炭素へ期待の取り組み」次世代ガスタービン~東北電力 上越火力発電所~
要約版|全文(PDF) - 514号(2022年9月)
「脱炭素へ期待の取り組み」アンモニア発電②~株式会社JERA碧南火力発電所~
要約版|全文(PDF) - 513号(2022年7月)
「脱炭素へ期待の取り組み」アンモニア発電①~国立研究開発法人 産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所(FREA)~
要約版|全文(PDF) - 512号(2022年5月)
「革新的な取り組み」CO2 回収・貯留技術CCS~苫小牧CCS 実証試験センター~
要約版|全文(PDF) - 511号(2022年3月)
「注目の新技術」再エネで水素製造 〜福島水素エネルギー研究フィールド〜
要約版|全文(PDF) - 510号(2022年1月)
「注目の再エネ」地熱発電 〜松川地熱発電所〜
要約版|全文(PDF) - 509号(2021年11月)
「低炭素を目指して」 CO₂ 低減技術IGCC(石炭ガス化複合発電)〜勿来IGCC発電所〜
要約版|全文(PDF)
放射線のおはなし
- 525号(2024年7月)
PETの原理 - 524号(2024年5月)
認知症の新しい治療薬と核医学診断 - 523号(2024年3月)
地震と放射線 - 522号(2024年1月)
がん抑制遺伝子「BRCA1/2」の変異による発がんとがん治療 - 520号(2023年9月)
X線CTの原理についての話 - 519号(2023年7月)
放射線によるDNA損傷の修復と遺伝子変異 - 517号(2023年3月)
反物質の話 - 516号(2023年1月)
宇宙旅行では、どの位被ばくするのか - 515号(2022年11月)
炭素14 の測定、それはロマンをかき立てる - 514号(2022年9月)
CT検査を受けるとがんになるリスクは増加するのか - 513号(2022年7月)
宇宙放射線~遠い星からのメッセージ - 512号(2022年5月)
転移のある前立腺がんの核医学治療 - 511号(2022年3月)
身の回りの放射性物質 空気中を浮遊しているラドン222 とラドン220 - 510号(2022年1月)
重粒子線(炭素線)による放射線治療 - 509号(2021年11月)
身の回りの放射性物質 カリウム40の環境への影響(お詫びと訂正)本文の内容に一部誤りがありました。正しくは以下のとおりです。
お詫びし訂正いたします。[24ページ] 2段
23行目 0.0062 → 0.0000062 mSv/Bq 26行目 0.12 → 0.00012 mSv 27行目 0.0062 → 0.0000062 mSv/Bq [25ページ] 1段
3行目 0.013 → 0.000013 mSv/Bq 9行目 0.13 → 0.00013 mSv 10行目 0.013 → 0.000013 mSv/Bq - 508号(2021年9月)
ホウ素中性子捕捉療法 - 507号(2021年7月)
身の回りの放射性物質 カリウム40とは? - 506号(2021年5月)
がんと遺伝子変異と放射線 - 505号(2021年3月)
三朝温泉の放射性物質のはなし - 504号(2021年1月)
トリチウムの健康への影響はどの程度なんですか? - 503号(2020年11月)
玉川温泉の放射性物質のはなし - 502号(2020年9月)
LNT仮説とCTによる医療被ばくについて - 501号(2020年7月)
放射線を用いて蟻を分析する - 500号(2020年5月)
放射性医薬品を注射してがんを治療するアルファ線内用療法 - 499号(2020年3月)
放射線を用いると簡単に元素を調べることができる - 498号(2020年1月)
輸血用血液製剤への放射線照射のはなし - 497号(2019年11月)
台風19号と放射線 - 496号(2019年9月)
医療機器への放射線照射のはなし - 495号(2019年7月)
鹿児島県のラジウム温泉のはなし
教えて!坪倉先生 気になる“ ほうしゃせん”
- 525号(2024年7月)
放射線被ばくで甲状腺がんが増える? ーその2ー - 524号(2024年5月)
放射線被ばくで甲状腺がんが増える? ーその1ー - 523号(2024年3月)
内部被ばくは、どうだったの? ーその2ー - 522号(2024年1月)
内部被ばくは、どうだったの? ーその1 ー - 521号(2023年11月)
放射線被ばくは遺伝するの? ―その2― - 520号(2023年9月)
放射線被ばくは遺伝するの? ―その1― - 519号(2023年7月)
トリチウムって、なに? ―その2― - 518号(2023年5月)
トリチウムって、なに? ―その1―
エネルギーを学ぶ・伝える ・考える
- 525号(2024年7月)
福島市立松陵中学校(福島県福島市) - 524号(2024年5月)
仙台市立岡田小学校(宮城県仙台市) - 523号(2024年3月)
大仙市立大曲南中学校(秋田県大仙市) - 522号(2024年1月)
気仙沼市立津谷中学校(宮城県気仙沼市) - 521号(2023年11月)
大鰐町立大鰐中学校(青森県南津軽郡大鰐町) - 520号(2023年9月)
学校法人福井学園 福井南高等学校(福井県福井市) - 519号(2023年7月)
魚沼市立広神西小学校(新潟県魚沼市) - 518号(2023年5月)
八戸市立白山台中学校(青森県八戸市) - 517号(2023年3月)
福島市⽴福島第一中学校(福島県福島市) - 516号(2023年1月)
⼭形県⽴⼭形⼯業⾼等学校(⼭形県⼭形市) - 515号(2022年11月)
七ヶ宿町立七ヶ宿中学校(宮城県刈田郡七ヶ宿町) - 514号(2022年9月)
福島県立福島高等学校(福島県福島市) - 513号(2022年7月)
佐渡市立二宮小学校(新潟県佐渡市) - 512号(2022年5月)
岩手県立一関工業高等学校(岩手県一関市) - 511号(2022年3月)
秋田県立秋田工業高等学校(秋田県秋田市) - 510号(2022年1月)
いわき市立中央台東小学校(福島県いわき市) - 509号(2021年11月)
新潟市立真砂小学校(新潟県新潟市) - 508号(2021年9月)
弘前市立新和中学校(青森県弘前市)神田 昌彦氏 - 507号(2021年7月)
山形県立酒田光陵高等学校(山形県酒田市) - 506号(2021年5月)
気仙沼市立階上中学校(宮城県気仙沼市) - 505号(2021年3月)
岩手大学(岩手県盛岡市) - 504号(2021年1月)
東北大学大学院工学研究科 量子エネルギー工学専攻(仙台市青葉区) - 503号(2020年11月)
仙台市立南小泉小学校(仙台市若林区) - 502号(2020年9月)
福島県環境創造センター交流棟 コミュタン福島(福島県田村郡三春町) - 501号(2020年7月)
宮城教育大学(宮城県仙台市) - 500号(2020年5月)
東北放射線科学センター(宮城県仙台市)
エネルギー学びの場 -エネルギー施設訪問-
エネルギー情報誌「ひろば」では、エネルギー施設を訪問しながら、現在のエネルギーの問題やその対応策について紹介しています。
| 号 | 発行年月 | 訪問先 |
|---|---|---|
| 499 | R2/03 | 南相馬変電所 東北電力株式会社 |
| 498 | R2/01 | 下郷発電所(揚水発電所) 電源開発株式会社 |
| 497 | R1/11 | 新北海道本州間連系設備 北海道電力株式会社 |
| 496 | R1/09 | 新信濃変電所 周波数変換設備 東京電力パワーグリッド株式会社 |
| 495 | R1/07 | 未来創電上北六ケ所太陽光発電所 未来創電上北六ケ所株式会社 |
| ユーラス小田野沢ウインドファーム 株式会社ユーラスエナジー小田野沢ウインドパーク |
||
| 494 | R1/05 | 中央給電指令所 東北電力株式会社 |
ちいき元気レポート

とうほく元気レポートは、「ひろば」のリニューアルにともない「ちいき元気レポート」に名称を変更いたしました。
- 2020年4月1日
色とりどりのニットを武器に変化する時代を乗り越える「株式会社大三」 - 2020年1月30日
本物の追求で世界に挑戦する「山崎金属工業株式会社」 - 2019年12月6日
地元の素材を使ったお菓子づくりで広がる笑顔とチャレンジの輪「みちのく創彩菓子 砂田屋」 - 2019年10月1日
手のひらに収まる「小さな奥入瀬」で人に感動を与えたい「奥入瀬モスボール工房」 - 2019年8月1日
英国から学んだ技術を礎に、「本格靴」を生み出す「宮城興業株式会社」 - 2019年5月27日
伝統の樺細工に新しい風を吹き込む「冨岡商店」
とうほく元気レポート

2019年
- 2019年5月9日
ものづくりの経験を活かした燻製技術で、 素材以上の旨味を引き出す「タムラ電子株式会社 食品事業部・スモークハウス」 - 2019年3月25
日寄磯浜で育った海産物の美味しさを毎日手軽に堪能してほしい「マルキ遠藤株式会社」 - 2019年2月28日
多彩な色合いと職人技が生みだす、青森の伝統工芸品「津軽びいどろ」 - 2019年1月28日
日常の中に豊かな食文化を育む「うるおい春夏秋冬(ひととせ)」
2018年
- 2018年12月18
日みんなで新しい新潟を切り拓く「新潟開港150周年記念事業」 - 2018年10月5日
地域の資源を見直し、魅力を創出する「野出島地域活性化プロジェクト」 - 2018年9月4日
幻の米「さわのはな」を通して、多くの人に喜びを届けたい - 2018年8月1日
枝豆を中心に異業種が繋がり、新しい町の名物を作り出す - 2018年7月1日
地元の資源や風土を活かし、「笑顔の食卓」を届ける老舗会社 - 2018年6月1日
北の海が育んだ「八戸前沖さば」をブランド化、美味しさを全国に - 2018年5月1日
地域資源を生かした商品開発で石巻の産業復興に挑む - 2018年4月2日
スイーツで若い世代の雇用を生み出し、地域の活力を取り戻そう! - 2018年3月1日
自分たちの手で、農業を地域活性化の一つに - 2018年2月1日
学校が新たなコミュニティーの場へ「橋本五郎文庫」 - 2018年1月5日
世界初の取り組みで、地域の魅力を全国に発信
2017年
- 2017年12月1日
日本の豊かな食文化を支える「糀」を次世代につなぐ - 2017年10月2日
独自の栽培で「吟壌果物」をブランド化「フルーツ王国ふくしま」を全国に発信 - 2017年9月1日
町に賑わいを!思いを一つにさらに前へ - 2017年6月22日
日本最大級の遺跡を世界に発信 - 2017年5月31日
糸魚川の大火からの復興を、地元のおいしさで支える老舗
推薦ひろば11冊
過去の「ひろば」100冊以上の中から、当懇談会がカテゴリー別にお薦めの”一冊”としてピックアップしました。
カテゴリー別に11冊を推薦します。内容は各リード文で確認下さい。その後、魅力を語るビデオ(約7分)、要約版(文字、約12分)、全文録(文字、約50分)でお楽しみ下さい。
暮らしとエネルギー
〔対談〕エネルギー利用者としての基礎教養 弘前大学教育学部教授 日景弥生氏、フリーアナウンサー 葛西賀子氏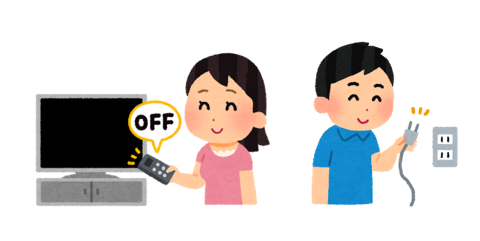 合成洗剤の環境負荷問題は30年前に解決したはずなのに、未だに有害だと言われるのが不思議であり、これは原子力問題にも通じると考えている。
合成洗剤の環境負荷問題は30年前に解決したはずなのに、未だに有害だと言われるのが不思議であり、これは原子力問題にも通じると考えている。大学の授業では、学生へのアンケートや環境家計簿で「見える化」し、エネルギーの話をするが、回答を見るとエネルギー自給率と原子力発電の関係では矛盾するのに本人は気付いていない。 自分が出すCO2量への理解とそれを減らすための一歩を、と熱く語る。
経済とエネルギー
エネルギー政策で幸せを創ることは可能か 常葉大学経営学部教授、NPO法人国際環境経済研究所所長 山本隆三氏 我が国の世帯平均収入は減り続け、国民の幸福度も低下。幸福度を上げるには安い電気が重要だが、三重苦(化石燃料の輸入増加、円安、FIT)で電気料金が大幅に上昇していると指摘。
我が国の世帯平均収入は減り続け、国民の幸福度も低下。幸福度を上げるには安い電気が重要だが、三重苦(化石燃料の輸入増加、円安、FIT)で電気料金が大幅に上昇していると指摘。米国ノーベル経済学者のポール・クルーグマンの言葉「医療、教育、電気は市場に任せてはいけない」、そして英国における原子力利用と利用しないリスクの比較、目に見えにくい便益等の考え方を紹介し、日本に警鐘を鳴らす。
エネルギー安全保障
第4次産業革命とエネルギー 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特任教授 遠藤典子氏 第四次産業革命により電力消費が増加する可能性があり、主力産業を支えるインフラとして安定的な電力供給が重要。現状の割高な電気料金と不安定な電力供給では、我が国の産業が世界市場で競い負けることを懸念。
第四次産業革命により電力消費が増加する可能性があり、主力産業を支えるインフラとして安定的な電力供給が重要。現状の割高な電気料金と不安定な電力供給では、我が国の産業が世界市場で競い負けることを懸念。エネルギー安全保障の観点から、エネルギー資源の多くを中東に依存しているリスクを十分認識することが必要であり、強い財務基盤を持つ原子力事業者実現のための政策が重要と提言。
エネルギーの現場
〔寄稿〕震災から7年、女川は今 科学ジャーナリスト 東嶋和子氏 震災後、女川原子力発電所の現場を担っている東北発電工業の社員が、東北電力社員と共に、使命感を持って復旧作業に取り組んできた姿を描く。
震災後、女川原子力発電所の現場を担っている東北発電工業の社員が、東北電力社員と共に、使命感を持って復旧作業に取り組んできた姿を描く。そして、津波を受けた近隣住民を300人以上も受入れて献身的に対応する発電所PRセンターの姿、女川町が新たに挑戦する数々の自立への道、また、その中で変わる発電所との関係など、町の復興が次第に進み見えてきた姿を温かい目を通して描き伝える。
エネルギー政策
いま、何を議論すべきなのか? 21世紀政策研究所研究主幹(当時) 澤昭裕氏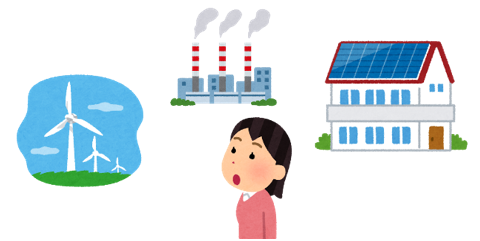 「エネルギー政策は何かを達成するための手段としてエネルギーをどうするのかの話であって、好き嫌いや事業意欲でエネルギーを選択する政策はあり得ない」という視点は、今後のエネルギー政策の中心にすべきポイントである。
「エネルギー政策は何かを達成するための手段としてエネルギーをどうするのかの話であって、好き嫌いや事業意欲でエネルギーを選択する政策はあり得ない」という視点は、今後のエネルギー政策の中心にすべきポイントである。また、原子力発電所停止による老朽火力の稼働増加は、停電の可能性が出てくるとの言及は(2015年当時)、その後の「北海道のブラックアウト」(2018年)を考えると氏の慧眼に感服する。
原子力の必要性とリスク
原子力に未来はあるか 国際環境経済研究所理事・主席研究員 竹内純子氏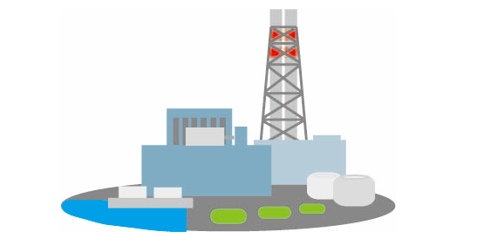 原子力の必要性とリスクの観点から、現在の我が国の電気の脆弱性を説明。その上で、原子力のメリットを享受するのか、放棄して原子力のリスクから解放される代わりに他のリスクを受容するのか、覚悟を持って判断する必要があると、我々にエネルギー選択の意思決定プロセスへの参画を求める。
原子力の必要性とリスクの観点から、現在の我が国の電気の脆弱性を説明。その上で、原子力のメリットを享受するのか、放棄して原子力のリスクから解放される代わりに他のリスクを受容するのか、覚悟を持って判断する必要があると、我々にエネルギー選択の意思決定プロセスへの参画を求める。また、原子力の未来のために立地地域への貢献の見える化など、興味深い4つの提言が示されている。
地球温暖化
これからのエネルギーと地球温暖化問題について考える 一財 日本エネルギー経済研究所 地球温暖化政策グループ研究主幹 小川順子氏 世界的な視野でエネルギーと地球温暖化問題について分析してみると、40年前も今も世界で使われているエネルギーの約8割が化石燃料という現実の中で、今後の途上国の人口増加と経済発展によるエネルギーと地球温暖化が大きな問題となるのは目に見えている。
世界的な視野でエネルギーと地球温暖化問題について分析してみると、40年前も今も世界で使われているエネルギーの約8割が化石燃料という現実の中で、今後の途上国の人口増加と経済発展によるエネルギーと地球温暖化が大きな問題となるのは目に見えている。これらへの対策は、省エネと低炭素エネルギーの最大限の活用であり、”電源のベストミックス“こそが最も重要なことである、と説く。
放射線と健康
放射線と健康 東北放射線科学センター理事長 宍戸文男氏 「チェルノブイリ事故との比較」(放出放射能量、避難基準、食品検査体制)、「福島県民健康調査結果」、「国際機関の報告」を基にしながら、福島県民に、原子力事故による放射線の健康影響は”ない”と結論付け、寧ろ避難生活による心身への影響を懸念している。
「チェルノブイリ事故との比較」(放出放射能量、避難基準、食品検査体制)、「福島県民健康調査結果」、「国際機関の報告」を基にしながら、福島県民に、原子力事故による放射線の健康影響は”ない”と結論付け、寧ろ避難生活による心身への影響を懸念している。また、将来の健康障害に関して、東京都民の半数が、福島県民に何らかの健康影響が起きると考えていることにショックを受けたと語る。
高齢化社会とエネルギー
エネルギー施策の課題と今後進むべき道 NPO法人社会保障経済研究所代表 石川和男氏 高齢化大国、介護大国の我が国で、今後ますます増大する社会保障費と消費税増税の関係をきめ細かく説明し、こうした状況下で、国民生活を支えるためには、「安価で安定」した電気の供給が重要と強調。
高齢化大国、介護大国の我が国で、今後ますます増大する社会保障費と消費税増税の関係をきめ細かく説明し、こうした状況下で、国民生活を支えるためには、「安価で安定」した電気の供給が重要と強調。大震災後の火力発電の増加等による電気料金の上昇、再エネの不安定性、低いエネルギー自給率を指摘し、こうした我が国独自の実情を反映した「エネルギー基本計画」の見直しを提案。
メディアの性質
世の中を動かす力は何か 毎日新聞社生活報道部編集委員 小島正美氏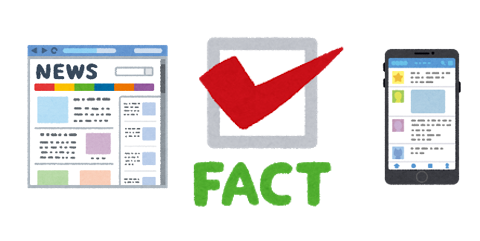 「科学的な話より面白い話」、「安全よりも怖い話」、「統計的な話より例外的な話」がニュースになる方程式と理解し、その上でメディアと上手に付き合うための具体的なアクションを提案。
エネルギーの分野も「科学者の多数意見が伝わっていない」ことや「個人的な生き方」と「国家の政策」を混同して報道される傾向があるなどから、メディア以外の情報も含め、自分で判断することが最重要と強調。
「科学的な話より面白い話」、「安全よりも怖い話」、「統計的な話より例外的な話」がニュースになる方程式と理解し、その上でメディアと上手に付き合うための具体的なアクションを提案。
エネルギーの分野も「科学者の多数意見が伝わっていない」ことや「個人的な生き方」と「国家の政策」を混同して報道される傾向があるなどから、メディア以外の情報も含め、自分で判断することが最重要と強調。
日本の歴史とエネルギー
地形から読み解く日本文明 NPO法人日本水フォーラム代表理事、東北大学客員教授 竹村公太郎氏 エネルギーを切り口に歴史を語るスタイルが新鮮。日本の遷都(奈良、京都、江戸)は、生活に必要なエネルギーである 「森の存在」から始まったと説く。
奈良には、人口10万人分の生活に必要な年間100万本の木の調達が可能、との判断があって遷都したと推定している。京都や江戸への遷都もこの「木」の存在(エネルギー)が理由であることを、地形的分析や広重の絵などの事実から解き明かす。
エネルギーを切り口に歴史を語るスタイルが新鮮。日本の遷都(奈良、京都、江戸)は、生活に必要なエネルギーである 「森の存在」から始まったと説く。
奈良には、人口10万人分の生活に必要な年間100万本の木の調達が可能、との判断があって遷都したと推定している。京都や江戸への遷都もこの「木」の存在(エネルギー)が理由であることを、地形的分析や広重の絵などの事実から解き明かす。

